こんにちは。かずきです。
ADHDの特性として、「気づいたら物が増えている」「片付けてもすぐ散らかる」「衝動買いが止まらない」といった悩みを抱える人は多いのではないでしょうか?
実際、私は部屋が散らかり放題で、探し物をする時間が増えるばかり。片付ける意欲はあっても、どこから手をつけていいのか分からず、結局途中で放り出してしまうことがよくありました。
そこで私は持ち物を減らし、シンプルな生活を送るミニマリズムを取り入れることで、整理整頓がしやすくなり、生活の質がアップしました!
本記事ではADHDとミニマリズムの「相性の良い点」と「相性の悪い点」をそれぞれ10個ずつ紹介したいと思います!

【プロフィール】
- 年齢:30代
- 住んでいる場所:大阪
- 診断:ADHD・うつ病(障がい等級:2級)
- 職業:特例子会社の正社員(障害者雇用)
ADHDとミニマリズムが相性の良い点(メリット10選)

視界の刺激が減り集中力が向上する
ADHDの人は周囲の物事に注意が散りやすい傾向があります。
ミニマリズムによって部屋の中の余計な物を減らすと、視界から入る情報量が減り、気が散る要素が少なくなるため集中しやすくなります。
散らかった環境では注意散漫や集中困難といったADHD症状が悪化しがちですが、持ち物を絞り込むことでその悪循環を断ち切る効果が期待できます。
ストレスや不安が軽減し、心が落ち着く
家の中がモノであふれていると、人は無意識のうちにストレスを感じます。
ある研究によると、
散らかった住環境にいる人ほどストレスホルモン(コルチゾール)の値が高く維持される。Clutter…How It Affects Both Your Physical & Mental Health
私はADHDの特性ゆえ、突然エンジンがかかったように家の掃除・整理整頓をすることが多いのですが、終わった後は確かにスッキリした気分になります。
自己コントロール感が高まり、過剰な刺激に振り回されなくなる
ADHDの人は外部からの刺激や誘惑に流されやすく、「気がついたら不要なものを買っていた」「目の前のことに翻弄されて一日が終わった」ということが起こりがちです。
ミニマリズムを取り入れると、身の回りのモノや情報を意識的に制限するようになるため、自分にとって本当に必要なものとそうでないものを見極める力が養われます。
実際私は、一人暮らしを始めた時は自動食器洗い機などの便利家電をたくさん買っていましたが、よく使うものとそうでないものが分かれてきて、不要になったものを処分したことで本当に必要な家電だけが残り、必要なものとそうでないものが分かるようになってきました。
片付け・掃除が簡単になり、日常管理の負担が減る
持ち物の量が減れば、当然ながら部屋が散らかりにくくなります。
散らかっていなければ、掃除をするのももちろん楽になります。
ADHDの私にとって掃除をする習慣をキープするのは苦労していますが、ミニマリズムによって掃除をするハードルそのものを下げることで、習慣的に掃除を継続することができています。
探し物が減り、物をなくしにくくなる
ADHDの人は物をどこに置いたか忘れてしまい探し回る、といった経験を持つ方も多いでしょう(ADHDなどの発達障害者以外でも思い当たる人はいるかもしれません)。
ミニマリズムで持ち物を厳選し定位置を決める習慣がつくと、必要なものをすぐに見つけられるようになります。
例えば重要な書類や請求書も、物が少なければ家中に紛れて行方不明…というリスクが減ります。
物を探す時間が減れば、その分だけ他の活動に時間とエネルギーを使えるようになるため、生活全体の効率が上がるメリットもあります!
財布や鍵は目立つところに置くように決めています!

選択肢が絞られ意思決定が楽になる
ミニマリズムでは持ち物を減らし必要最小限の選択肢に絞るため、日々の小さな意思決定に費やす労力が減少します。
私は服を減らしたおかげで身支度をするのがとても楽になりました。
仕事用のシャツ5着とジャケット・パンツ2着、休日用のパーカーやTシャツ2着とジーパンのように、1週間のコーディネートを決めておくとそれ以上決断する必要がなくなり非常に楽になりました。
衝動買いや無駄遣いが減り、消費行動が改善する
ミニマリズムを志向すると「本当に必要な物か?」と自問する習慣が身につくため、ADHDの人が陥りがちな衝動買いや浪費の抑制にもつながります。
なるべく物を増やしたくないという気持ちが先行するようになれば、本当に必要なものしか買わないという思考になるので、無駄な買い物が少なくなりました。
節約効果が期待でき経済的メリットもある
上記のように無駄な買い物が減れば、当然お金の節約につながります。
ADHDの人は興味の赴くままに散財してしまったり、管理不足で追加出費が発生したりしがちですが、持ち物と支出を絞り込むミニマルな暮らしは金銭面の安定にもつながるでしょう。
実際私は障害者雇用で働いており給料が少ないのですが、無駄遣いがないことで貯金を継続することができています。
生活全体の優先順位が明確になり、本当に大切なことに集中できる
ミニマリズムを通じて「自分にとって必要なもの・大切なことは何か」を見つめ直すうちに、生活の優先順位がクリアになります。
これは物質面にとどまらず、時間の使い方や人間関係にもつながります。
このようにミニマリズムは生活全般のシンプル化につながり、ADHDの人が自分にとって大切なことにエネルギーを振り向ける手助けとなります。
対人面やメンタル面での好影響も期待できる
部屋がごちゃごちゃだと人を家に招くのが恥ずかしくて避けてしまう…という話を聞くことがあります。
ミニマリズムによって家がスッキリ片付けば、そうした恥ずかしさや後ろめたさが減り、人付き合いを積極的に楽しめるようになるかもしれません。
生活空間が整うと自己評価も高まりやすく、「自分はちゃんとできている」という自信がつくことでメンタルヘルスの向上にもつながるでしょう。
ADHDとミニマリズムが相性の悪い点(デメリット・注意点10選)
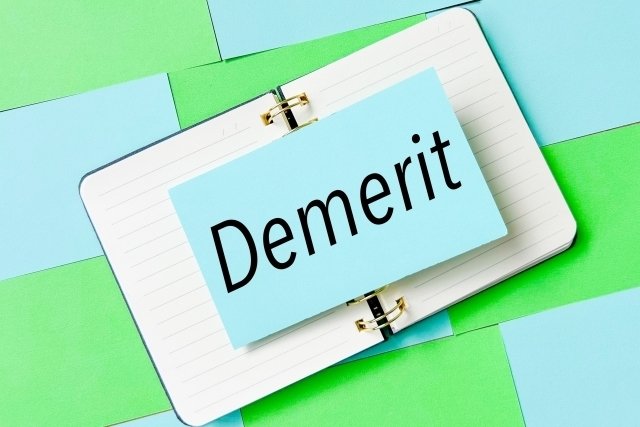
衝動性や収集癖がミニマリズムを妨げやすい
ADHDの特性である衝動性は、ミニマリズムとの相性を悪くする代表的な要因です。
欲しいものが目に入るとつい買ってしまったり、一時的な熱中で趣味の道具を一気に揃えてしまったりと、衝動的な行動で持ち物が増えやすい傾向があります。
私はガジェット類が大好きで、iPadの最新モデルが出るとつい購入してし待って大きな出費につながってしまうことも・・・
対策としては、**「本当に必要かどうか1週間考える」**ようにして、冷静に判断できるようにしています。
片付けや整理整頓の習慣を維持するのが難しい
仮に一度大規模に断捨離して物を減らせても、それを維持する習慣化が難しい場合があります。
ADHDの人は継続的なルーティン作業が苦手で、「最初は頑張って片付けても気づけば元通り散らかっていた」という“リバウンド”が起こりがちです。
完璧なミニマリズムを達成しなければならないというプレッシャーを手放そうWhy Minimalism Isn’t Always the Answer for ADHD Clients
雑誌やYouTuberのような完璧なミニマリズムをしようとしてもADHDにとっては息切れしてしまう可能性が高いです。
まずは1カ所だけ片付けるというようにハードルを下げるのが継続のポイントです。
大がかりな断捨離に圧倒され、先延ばししてしまう
ミニマリズムを始めようとしても、「物が多すぎてどこから手を付ければいいか分からない」「一気に片付けようとして疲れてやめてしまった」というケースもあります。
ADHDの人はタスクが大きすぎたり先が見えないと感じたりすると、圧倒されて先延ばし癖が出やすい傾向があります。
実際、「家全体を一気に片付けようとしたら途中で嫌になってやめてしまい、余計ひどい有様になった」という声もSNS上にはあります。
このように、ミニマリズムの第一歩である“物を減らす”段階で挫折してしまう場合が少なくありません。
「見えないと忘れる」問題で収納があだになる
ADHDの特性として、視界に入らないものは頭から抜け落ちてしまう(オブジェクト・パーマネンスの欠如)というものがあります。
せっかく物を片付けて収納しても、それをしまい込んだ途端に存在を忘れてしまい、必要なときに思い出せないということが起こりえます。
クリアな収納ボックスやラベルで中身が一目で分かる工夫をするなど、中身が一目でわかる工夫をするのが良いでしょう。
私はオープンラックを活用して、目に見える収納を意識しています。
ちょっと散らかっているように見えるけど、これくらい緩くやるのも継続のポイント

物への愛着や「いつか使うかも」という不安で手放せない
不要な物は捨てれば良いと頭では分かっていても、実際には感情的な障害がそれを難しくします。
ADHDの人は「捨ててしまったら大切な記憶まで失う気がする」と感じたり、「今は使ってないけど将来必要になったらどうしよう」と不安になったりして、なかなか手放せなくなることも少なくありません。
私は対策として、色紙などのプレゼントを写真にとって、デジタルで保存するなど、デジタル化することで物を減らしつつ思い出を残す手段をとっています。
すぐに結果が見えづらくモチベーションを維持しにくい
ミニマリズムの効果――例えば「部屋がスッキリして気持ちいい!」と実感できるまでには多少の時間と労力が必要です。
ADHDの人は飽きっぽかったり結果がすぐ出ないとやる気を失ったりしやすいため、片付けの途中で投げ出してしまうことが考えられます。
対策としてこまめに達成感を得られる工夫(後述する小分け作業など)をしないと、途中で息切れしやすいでしょう。
シンプルすぎる空間が刺激不足で退屈に感じる
ミニマリストの部屋によくある白やベージュ中心で物がほとんど置かれていない空間は、一部のADHDの人にとって「味気ない」「落ち着かない」と感じられる場合があります。
ADHD脳は適度な刺激があった方が活性化することもあり、極端にミニマルで無機質な環境では逆に集中力やモチベーションが下がってしまうこともあるのです。
ミニマリズムの美学を追求しすぎて生活空間から刺激や個性を無くしすぎると、ADHDの人にとっては落ち着くどころか逆効果になる可能性があります。
勢いで物を捨てすぎて後悔するリスクがある
ミニマリズムに傾倒するあまり、必要なものまで処分してしまって後から後悔するケースも考えられます。
特にADHDの人は思い立ったら一直線に行動してしまう傾向があるため、「断捨離だ!」と一気に捨てたはいいものの、後になって「やっぱりあれは必要だった」と気づくこともありえます。
何でもかんでも捨てれば良いというわけではなく、自分にとって重要なものとそうでないものを見極める冷静さが求められます。
さもないと、ミニマリズム実践後に「必要な物まで無くなって不便になった…」と本末転倒な結果になりかねません。
私はニンテンドースイッチを勢いで売ったはいいものの、「またあのゲームやりたい・・・」という衝動にかられ、後悔を感じることが少なくありません。
興味関心の幅広さゆえに必要最低限を絞るのが難しい
ADHDの人は好奇心旺盛で趣味や関心がコロコロ変わりやすい傾向があります。
ある時期は音楽にハマり、その後は急にキャンプに熱中する…といった具合に興味が移り変わるため、その都度道具や材料が増えていきます。
ミニマリズムでは「使っていない物は処分する」ことが推奨されますが、ADHDの人の場合「今は使っていないけど、またそのうちこの趣味に戻るかも…」と思うとなかなか捨てられません。
また、仮に思い切って処分してしまうと、後日再び同じ趣味に熱が再燃して買い直す羽目になることも考えられます。
興味の対象が多岐にわたる人ほど持ち物の取捨選択が難しく、「これさえあれば十分」と必要最低限を決めづらいというジレンマがあります。
結果として、ストイックなミニマリズムを貫くのが難しく感じるかもしれません。
完璧なミニマリストを目指すとプレッシャーやストレスになる
前述のように、雑誌やSNSで見るような完璧なミニマリスト生活を実現しようとすると、ADHDの人にはかえってストレスになる恐れがあります。
ミニマリズム本来の目的は人生を豊かにすることであって、人を追い詰めることではありません。
にもかかわらず、「もっと物を減らさなきゃ」「まだミニマリストとして甘い」と自分を責めてしまうと本末転倒です。
ADHDの人がミニマリズムに取り組む際は、完璧さより継続しやすさを重視することが大切でしょう。
結論:ADHDの人がミニマリズムを無理なく続けるための工夫
ADHDとミニマリズムには相性の良い点・悪い点の両方があります。
ミニマリズムのメリットを最大限に享受するために、ADHDの特性に合わせてミニマリズムを「自分流」にアレンジすることがカギとなります。
完璧を目指さず「ゆるいミニマリズム」を心がける
無理にインテリア雑誌のような完璧な空間を作ろうとせず、自分にとって心地よい範囲で物を減らしましょう。
多少散らかっても気にしすぎない「メッシー・ミニマリズム(散らかっていてもOKな最小主義)」という考え方も提唱されています。“Messy Minimalism” My ADHD-Friendly Approach to Decluttering
自分のペースで少しずつ進め、理想とのズレに過度なストレスを感じないようにすることが長続きの秘訣です。
小さく始めて徐々に進める
最初から家全体を片付けようとせず、まずは一箇所(引き出し一つ、机の上など)から始めるのがおすすめです。
達成したら次…と少しずつ範囲を広げていけば、達成感を積み重ねながら進められます。
作業を「今日は机の上だけ」「明日はクローゼットの下段だけ」のように細かく区切ると、ADHDの人でも飽きにくく先延ばしにしにくくなります。
一度に全部やろうとすると燃え尽きてしまうので、少しずつでも継続することを重視してください。
見える化収納を活用する
物を減らしつつも、必要なものは見えやすく保管する工夫をしましょう。
例えば中身の見えるクリアボックスやラベリングを活用し、「何がどこにあるか」を一目で把握できるようにします。
こうすることで「しまい込んで忘れていた」という事態を防ぐことができます。
無印良品のボックスを活用

衝動買い対策を取り入れる
ミニマリズム継続の大敵である衝動買いを防ぐため、自分なりのルールを設けましょう。
買い物リストを作り計画的に購入する、欲しい物があればその場で買わず一定期間寝かせて本当に必要か考えるなどが効果的です。
自分に合ったミニマリズムのスタイルを見つける
ミニマリズムと言っても人それぞれです。ADHDの人にとっては、極端に物を減らすよりも必要なものは残しつつ余計な物を持たない「適度なミニマル」が現実的かもしれません。
趣味の物は厳選して残す、カラフルで好きなインテリアアイテムは置いておく、といったように自分の喜びや安心につながる要素は無理に排除しないことも大切です。
自分にとって本当に必要なものだけを残すという本質を押さえれば、形にとらわれない自分流のミニマリスト生活が実現できます。
必要に応じて支援を活用する
一人で片付けるのが難しい場合、信頼できる友人や家族に手伝ってもらったり、いわゆる「お片付けサービス」やコーチングを利用する手もあります。
誰かと一緒に進めれば途中で気が散りにくく、 Accountability(説明責任)も生まれるため、最後までやり遂げやすくなります。
周囲のサポートを適切に借りながら、自分ひとりで抱え込まないこともポイントです。
まとめ
ADHDの人にとってミニマリズムは諸刃の剣とも言えますが、デメリットに対する対策を講じつつ自分に合ったやり方で進めれば、メリットを大いに享受できます。
散らかった環境をシンプルに整えることは、集中力アップやストレス軽減などADHDの症状改善に役立つ可能性があります。
一方で、自分を追い込みすぎないよう「ゆるく・楽しく・マイペース」に取り組むことが長続きの秘訣です。
ミニマリズムの目的は人生を豊かにすることであり、決して苦行ではありません。
自分に必要なものを見極めて取捨選択するプロセス自体が自己理解を深め、ADHDとうまく付き合う助けにもなるでしょう。
ぜひ焦らず無理せず、自分なりの最適なバランスを見つけてみてください!
ミニマリズムはADHDのあなたの味方になり得るはずです。
この記事を読んでよかったと思った方はSNSなどでシェアしていただけると嬉しいです!



コメント